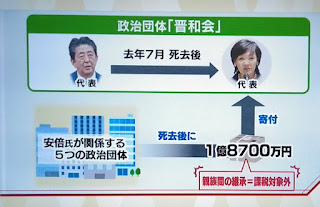旧秋田刑務所正門
〈100年前の世界166〉大正12(1923)年 大杉栄・伊藤野枝・橘宗一虐殺(㉓) 松下竜一『久さん伝』より 大正13(1924)年12月~大正14(1925)年9月 和田久太郎無期懲役(村木源次郎獄死、古田大次郎死刑) より続く
大正12(1923)年 大杉栄・伊藤野枝・橘宗一虐殺(㉔)
松下竜一『久さん伝』より
大正14(1925)年9月
9月19日、和田久太郎は市ヶ谷刑務所を出て、翌20日夜、秋田刑務所に着いた。
21日、和田は刑務所の運動場で北国の秋天を仰いで、その感慨を句にとどめている。
死ぬ迄の赤い衣か彼岸暗
11月6日、ようやく和田の所在を知った近藤憲二と望月桂が秋田刑務所を訪れた。
秋田駅から約2km郊外に刑務所はあった。横ざまに吹きつける霰(あられ)が音を立ててはじける刑務所の高塀を仰ぎ、近藤も望月も地の果てにきたような暗い思いに沈んだ。
しかし金網越しに会う和田は、柿色のぶくぶくした綿入れを着込んで、少し肥っているようにみえた。身体の調子のいいことを告げてから、和田が尋ねた。
「僕がここにきてからいちばん心配になっているのは古田君のことだ。どうなったろうか?」
二人がその問いに答えようとする前に、立合いの看守長が慌てて、「その話はいけない」とさえぎった。しかし、二人の無言の表情から和田は答を読みとったようであった。
近藤憲二は『労働運動』誌上での、古田大次郎の刑死と、秋田刑務所での和田との面会を報告した文章を、次のように結ぶ。
古田君は絞首台の上に倒れた。和田君は其の生涯を秋田の牢獄に送ろうとしている。僕等はそれを忘れない。古田君の首に残った紫色の紐(ひも)跡 - 。網笠をとって振り返った和田君の姿 - 。僕等はそれを忘れない。
刑務所から出す書信は2ヵ月に一度と制約されていて、家族相手にしか宥されぬので、中村しげ(望月福子の妹)を形式上和田の内縁の妻という届けにして、いっさいの書信のやりとりは、しげを通すことに定めた。
12月13日、和田の中村しげ子宛ての第一信が宥された。第一信で和田が訴えているのは、北国の冬の厳しさである。此の年はまだ積雪はみないが、毎日毎日風と霙(みぞれ)と霰が吹き荒れ、獄窓に仰ぐ空の暗さにめいっている。房内の気温は華氏13度というから、摂氏では零下10度である。もちろん、暖房具はない。
1926(大正15)年4月11日、第二信が宥された。
屋根の雪とどろと落ちて揺るる陽や
空へひたと顔つけて春を讃(たた)えけり
和田の老いた母か病身な義兄のどちらかが面会に来たがっていることを、しげが伝えると、和田は、どうか二人とも止めてくれと、彼女に頼んでいる。和田は、1920(大正9)年に父の死をみとったとき以来、もう5年余母と会っていない。
房内に母の幻をみて句を作る。
老母を包む冬の光線の濁(にご)る塵(ちり)
また、この第二信に、〈鉄君がまだ生きているなら「笑って死ね」と伝えてくれ〉と和田は記しだが、中浜鉄は4月15日堺刑務所で刑死していた。
1926年(大正15)年5月15日、和田は読書と筆墨の許可を得る。入所から半年という計算でいけば3月下旬には宥されているはずで、2ヵ月近くも遅れたのは、和田の反抗的態度に対する懲罰であったのかもしれない。あるいは、労役ノルマを達成できなかったということもあるかもしれない。靴下の先かがりという単純作業であるが、和田の能率はあまりよくなかったらしい。
筆墨が宥された日、ここ8ヵ月間に作った句や歌で記憶にとどめていたものを、一気に書き並べ、夜は『乞食桃水』に読みふけった。
6月10日付の第三信は悲痛である。
僕からの手紙は、今後雑誌に決して発表しないでくれ。ただ是非とも『労運』にだけは発表せねはならぬ場合は、極く簡単な消息だけ抜き書きにして発表してくれ。でないと、今後僕の手紙や俳句などがそのまま世間へ発表さるれば、「受刑者に社会の雑誌の原稿は書かせぬ」という理由から、君との文通は「厳密に是非必要用件の外は書かせない」と申渡された。旬や歌は勿論、公子に童謡を書くこともいけなく、且つ一寸した感想にしても「原稿じみる」の一言で片づけられる。知っての通り、不平や不満は勿論書かされない。そうなれば、「僕は毎日嬉しく感謝に満ちて働いている。皆んなに変りはないか」と二ヵ月に一度書けばお終いだ。そんなものなら僕は書きたくない。手紙をやらねば皆んなが心配しよう、僕にも楽しみや慰安がなくなる。・・・こういう訳だ。そして、「決して雑誌へ大びらに発表せぬ」という誓いの下に、この手紙及び今後の通信が今まで通り出来ようというのだ。
そんな馬鹿な事があるかっ。和田もそんな腰抜けになったか!! 卑屈だ!! と嘲罵する者が若しあったら、和田は其の嘲罵を笑って甘受する、と答えてくれ。
君からの手紙も、いつでも可なり切り取られる。殊に今度の手紙は「社会の出来事を沢山書いてあるから不許にする筈だが・・・」とて渡された。君は何枚薯いたか知らぬが、僕の見たのは三枚だ。それに、二三行の切っ端が二つ三つくっつけてあった。それだけだ。あれに望月が九州へ行った事と、ルイズの事とが少々あったので、僕は破り棄てた先の手紙に「マコの様子を知らせ」と書いた。ところが、これもいけないのだそうだ。「大杉の子供の消息などは断じてならぬ」という所長の意見だそうだ。この時ばかりは僕も口惜し涙がこぼれた。僕が大杉の子供の消息を知っちゃいけない・・・。何んという事だろうと思った。
「マコの様子を知らせ」と書いたのが検閲にひっかかって返され、久太郎は怒って荒れた。
叱責されて4日後に全面的に書き直したのが、この悲病な手紙だった。手紙の後半にみられるのは、諦めのみである。もともと和田には一種の恬淡味があるが、この投げやりな諦めには、たんに恬淡とはいえぬ痛ましさがのぞいている。
が、だ。が・・・・・僕はこれもあきらめる事にしたよ。ウン、あきらめたよ。だから、大杉の子供の事も今後知らせてくれても無駄だ。見せられない。同志の消息なんか勿論駄目だ。時事問題も知りたくない。『人』(刑務所用の雑誌)と『新聞年鑑』で沢山だ。書いて来るのは止してくれ、無駄だ。君自身のことでも、今後は沢山書いて来てくれ。君のいろんな感想もよかろう。公っペいの悪戯ぶりや、望月が商売に精出さない、絵も書かない、そのグチもよかろう。世間の事でも地下鉄道が出来たの、尾上栄三郎が死んだのはよかろうじゃないか。庭の草花は今年はどうだい。待宵草も大きくなったかい。お地蔵さんはどんな顔をしているかい。・・・まあ、そんな事でも面白可笑しく書いて来てくれ。僕も亦、雀や燕のいたずら振りでも書こうよ。胸につかえたり、腹に溜ったりする事は、すっぱり忘れよう。・・・これが僕をして「短気を出さしめない、負け嫌いをつっぱらせない」何よりの薬だ。そして「忘」と「無為」の妙味を説く禅書にでも親しみながら、けり、かな、とやっていよう。
同志との交渉を強制的に断ったなら、それで和田の心がすっかり変る - 長い間には ー というのが刑務所の自信だ。僕はただ、これに対して「微笑」をもって答えるのみだ。
和田が獄中のノートに次のように書き記したのは、この手紙の直後であったろうか。〈「総べてに負くるは総てに勝つ事なり」という、奇妙な、しかし確かに一つの真理である事を最初に悟った人間は、負け嫌いな人間という動物中の、最も負け嫌いな奴だったに相通ない〉
仏書や禅書や俳書に読みふけりながら、和田は自らを殺して平静に生きようとする。獄中で再びめぐってきた9月1日にも、〈人の問わば秋の黄雲を指ささむ〉という禅問答めいた句を詠んだのみである。
11月4日の第6信では、たしかに自分も落ち着いてきたと書く。刑務所側も和田の安定を認めたのか、かねてから本人が希望していた久留米がすりの機織り作業を許可したが、しかしこれは20日しか続くかかった。慣れぬ仕事で体調をくずしたために、また靴下の先かがりという単純作業に戻らねはならなかった。
12月25日、昭和改元。
1927(昭和2)年1月9日付けの手紙でも、和田は獄中での落ち着きを強調してみせる。
僕は最近徹底的に落着く事が出来るようになったように感ずる。外の事も大して気にしなくなったし、頭に詰め込んでいる生半熱な学問の片々など、すっかり捨ててしまいたいと思うようになった。その内に賞与金が溜ってくるから、年に二冊の本は買える事になる。だから本の事もそれで沢山だと思うようになった。一切の通信を断たれても、心静かに、落霜いて生きていられるという自信もついて来た。その点も決して心配してくれるな
裕仁践祚にょる恩赦で、無期懲役から20年の有期刑に減刑されたことも、予想外のことであっただけに和田に希望をもたらした。
4月には、近藤憲二の尽力で出版された『獄窓から』が届き、久太郎は感無量の思いで読みふけり落涙する。
5月11日には、中村しげが面会にきてくれた。彼女は『良寛和尚詩歌集』『一茶と良寛と芭蕉』『万葉全集』『万葉以後』と、『獄窓から』に寄せた芥川竜之介の批評の切抜きを持参していた。さらに、医師奥山伸からの伝言と10円の差し入れまで預かっていた。
芥川は東京日々新聞に寄せた書評のなかにこう書いている。
和田久太郎君は、この書簡の中に、君の心臓を現している。しかも社会運動家でも何でもないわれわれに近い心臓をあらわしている。僕はここに理性の力を云々しようとは思っていない。又和田君の心臓を云々しようとも思っていない。ただこの心臓の持ち主は、同時にまた唯物主義的に鋭い頭脳の持ち主だった。これは勿論和田君には悲劇的な矛盾である。しかし同時代に生まれ合あせたわれわれに共通する矛盾である。和田君はこの矛盾を持っているために必ずしも大を加えないかも知れない。けれどもとにかくわれわれには少からず親しみを加えるのである
こう書いた芥川が自殺するのは、このときから4ヵ月も経たぬ7月24日である。獄中の和田にもこのニースは知らされた。
〈地の下で虫の鳴く声をきかるるか〉と、芥川を悼む一句を残している。
どうやら平静な日々がつづくとみえた久太郎に、決定的な破局が訪れたのは9月である。
9月、平静な日々が続くとみえた和田久太郎に決定的な破局が訪れる。9月20日の手紙。
今から三カ月以後、囚人に対して私本を読ませる事が絶対に禁じられた。勿論当所だけというのではなく、全国一般なのである。が、私がこの事を聞いた時の失望と憤慨とがどんなに大きかったかは察してくれ給え。行刑局からの一般的達しとあれは、いくら当所長へ掛け合ったところで仕方のない話だとは思っても、残念さ口惜しさが胸先さへ込み上げてくる。私本が読めない位なら、暴れるだけ暴れて暴れ死んでやれ、というような自暴自棄的な考えが高まって来て、十八日から今日の昼まで暴れに暴れて、トンダ事をしてしまった。結局、明日私本全部をそちらへ送り返す事にしたのである。で、この手紙の着いてから間もなく、全部の本がそちらへ行き着く事と思う。
期間はまだ三ヵ月間ある。けれども、どうせ駄目なものなら、今からすっぱり思い切った方がよいと思うので、明日送り返す。これは君からの手紙にあったような、ひねくれ根性からでは毛頭ない。誤解せないようにしてくれ。
和田はけっきょくこの打撃から立ち直れなかった。
獄中ノートに残された最後の歌。
また誰か狂いゆくらしくろかねの窓の吹雪のひと日ひと日を
寂しさに狂える人をあざ笑う同じ囚徒の悲しくもあるか
1928(昭和3)年2月20日、秋田刑務所独房において和田久太郎自裁。縊死であった。満35歳になったばかり。
「大正12(1923)年 大杉栄・伊藤野枝・橘宗一虐殺(㉔) 松下竜一『久さん伝』より」終り
つづく